資格勉強を始めてみると、まず最初に迷うのが「教材をどうするか」じゃないでしょうか。
本屋さんに行けばテキストや問題集がずらっと並んでいるし、ネットで調べると通信講座やオンライン講座の広告も次々に出てきます。選択肢が多すぎて、逆に決められない……そんな気持ちになったのは、私だけじゃないと思います。
今回は、50代から勉強を始めた私が
・教材選びで感じたこと
・実際に手に取ってみた教材
・独学と通信講座の違い
などを、リアルな体験を交えながらまとめてみます。
これから勉強を始める方の参考になれば嬉しいです。
独学のメリット・デメリット
まずは独学。なんといっても一番のメリットは「お金がかからない」こと。
書店でテキストを買って、必要に応じて問題集や過去問を揃えていけば、数千円〜数万円で勉強がスタートできます。
一方で、独学にはやっぱりデメリットもあります。
特に大きいのは「自分で進めるしかない」という点。
何をどの順番で勉強するか、今の理解度で良いのか、わからないことがたくさん出てきます。
最近は、AIに相談すると学習スケジュールを組んでくれたり、何かと便利なこともあります。でもモチベーション管理も含めて、全部自分でやる必要がありますよね。
50代から新しい資格に挑戦する私にとっては、この「自分だけで続ける」という部分が一番のハードル。
なので「独学で行けるところまで行って、どうしても無理だったら通信講座を頼ろう」というスタンスにしています。
無料で学べるYouTube講座
最近はYouTubeでも質の高い解説動画がたくさん公開されていて、独学の強い味方になっています。私がチェックしているのはこの2つ。
【図解でわかる社労士講座】
難しい法律の内容を図やイラストを使ってわかりやすく解説してくれるチャンネル。
文章だけでは頭に入りづらい部分も、ビジュアルで見るとスッと理解できます。
【社労士24】
短時間で要点を絞って説明してくれるのが特徴。
すきま時間に見られるので「今日は疲れたけど10分だけ勉強しよう」というときにも役立っています。その他に勉強法の工夫あれこれも動画で見られます。
どちらも無料で利用できるので、まず「試しに勉強してみよう」という入り口にはぴったりではないでしょうか。
私も最初は動画を見ながら感覚をつかむところから始めました。
通信講座という選択肢
次に通信講座について。こちらもたくさんありますが、代表的なものの中から2つ挙げますね。
【アガルート】
社労士の通信講座といえば、最近はここを思い浮かべる人も多いと思います。
教材がシンプルで見やすく、動画講義もわかりやすいと評判。
合格実績の高さもあり「短期間で合格を狙いたい人」には人気があります。
特に添削や質問サポートがあるのは、やっぱり心強いですよね。
【フォーサイト】
カラフルで視覚的に理解しやすいテキストが特徴。通信講座の中でも古くからある大手で、オンライン学習システムも充実しています。
「映像講義+紙の教材+アプリで復習」といったハイブリッド型が合う人にはこちらがおすすめ。
通信講座は独学に比べてお金はかかりますが、その分「道筋を作ってもらえる安心感」があります。
実際に私が選んだ教材
ここで、私の体験を少し。
通学は、近くに通学予備校がないので、そもそも候補に入らなかったですね。
通信講座か独学か⋯と迷っていた時に、それぞれ「資料請求してみよう!」「本屋で見てみよう!」をやってみました。
まずは通信講座への資料請求から。
私が気になったのはアガルートの『合格特典』です。対象カリキュラムを受講して同年の社労士試験に合格した場合、最大で『受講料(税抜)の全額返金』の特典があるんです。
(※合格特典のご利用には条件があるので、気になる方はアガルートのホームページをチェックしてみてくださいね。)
資料請求をすると、すぐにサンプル講義映像などが送られてきました。
受講相談もあり試験への質問や勉強の進め方など相談できます。
合格体験記などもあってとても参考になりました。
けれど、社労士は難関資格。
合格特典を狙って受講しようと思っていたんですが、受からなかったら全額支払いです!
(当たり前です。)
ちょっとビビっちゃったんですよね。
特典を意識せず普通に受講することも考えたり、他の通信講座も視野に入れたりしてみましたが、このあたりから独学へとゆっくり方向転換していきました。
独学するならばと8月末に本屋へ行ったとき、まだ2026年版のテキストはTACの入門書しか出ていませんでした。ぱらっと中を見てみると、カラー部分が多くてわかりやすそう。でも比較したかったので、小さな本屋でも並んでいるTACとユーキャンに対象を絞り、まずはユーキャンの入門書をAmazonで購入して勉強を始めました。
実際に使ってみると「図解やまとめページがあって、初学者向けに親切だな」と感じています。ただ、入門書はあくまで全体像をつかむためのもの。10月になると本格的なテキストがTAC・ユーキャン両方から発売される予定なので、そのタイミングで今度はTACを試してみようと思っています。
こうやって教材を「試して比べながら進める」ことも、私にとっては勉強の一部。合う合わないは人によって違うので、気になるものは実際に手に取ってみるのが一番だと思います。
教材選びのポイント
私なりに考える「教材選びのポイント」は大きく3つ。
1. 価格とのバランス
続けられる金額かどうか。最初から高額な講座に申し込むと、もし続けられなかったときのダメージも大きいので要注意。ただし、高額だからこそ「やらなきゃ」とスイッチが入ることも。
2. わかりやすさ
テキストや講義の「自分との相性」が一番大事。評判が良くても、自分にとって理解しやすいかどうかは別です。
3. ライフスタイルに合うか
スマホで学習できるのか、紙テキスト中心なのか。仕事や家事の合間に使いやすい教材かどうかをチェック。
よくある疑問Q&A(公式データ+私の実感)
Q. 社労士試験の合格率ってどれくらい?
A. 第56回(令和6年度)の試験では、受験者数 43,174 人、合格者数 2,974 人で、合格率 6.9% という結果でした。(厚生労働省 第56回社会保険労務士試験結果より)
毎年 6%前後と、とても狭き門なんですよね。数字だけ見ると「厳しいなぁ」と感じますが、ちゃんと準備をすれば突破できる試験だとも言えます。
Q. 50代からでも挑戦できる?
A. 合格者の年齢別構成を見ると、50代の合格者は全体の約 19.2% を占めていました。(厚生労働省 第56回社会保険労務士試験結果より)
さらに最年長の合格者は 81 歳。年齢に関係なく挑戦できる資格だということがよくわかります。
「50代からじゃ遅いかな…?」と私も最初は思っていました。でも実際にデータを見ると「同世代もちゃんと頑張ってる!」と励まされましたし、むしろ経験を武器にできる部分もあるんじゃないかと思えるようになりました。
確かに体力面や暗記力は課題になりますが、経験や勉強法の工夫次第でカバーできると思います。教材や過去問を絞り込むことが大事ではないでしょうか。
朝の時間や通勤時間など「ルーティンに組み込む学習法」を意識すると、無理なく続けやすいようです。
Q. 合格率の低さと戦うにはどうすればいい?
A. 私自身まだ挑戦の途中ですが、合格率が低いからこそ、教材選び・勉強法・継続力が本当に大事だと感じています。
完璧じゃなくても、とにかく「毎日机に向かう」「隙間時間を積み上げる」ことが勝負かなと。
それに加えて、通信講座のようにサポートしてくれる存在を取り入れるのも一つの方法。
独学が合わなければ柔軟に切り替えるつもりでいます。
Q. 独学だけで社労士試験に合格できる?
A. 公的なデータで「独学で合格した人数」の統計はないですが、非常に稀という意見が多いようです。
ただし独学でも合格者はいます。
科目数が多いので計画的に進める必要があり、市販テキスト+過去問を何度も繰り返すのがカギになりそうです。
モチベーションを保つために「勉強記録アプリ」やSNSで仲間を見つけると続けやすいかも。
Q. ユーキャンとTACの違いは?
A. ユーキャンは「初学者でもわかりやすい基礎重視」、TACは「試験に直結する情報量とカラー解説」が特徴。自分の学習スタイル(コツコツ型 or 一気に詰め込み型)をイメージして選ぶとミスマッチが減ります。
また、テキストはこの他にもたくさん出版されています。
自分好みの一冊を見つけてくださいね。
Q. 通信講座って高いけど、本当に必要?
A. 通信講座はカリキュラムやスケジュール管理が整っているので、効率的に学習できます。
添削や質問対応があるのも大きなメリット。
費用が気になるなら「基礎だけ通信、演習は市販テキスト」といったハイブリッド型の学び方もgood。
Q. アガルートはどう?
A. 実は受講者の合格率も高めで、令和6年度では有料受講生の合格率が35.82%という情報があります。講義動画のクオリティに定評があり、質問対応が速いのも安心材料。
途中からでも受講できるので「独学で限界を感じたときの保険」として選ぶのもアリ。
Q. アガルートに資料請求をしたらどんなサポートが受けられるの?
A. 講義の無料サンプル映像(合計7時間)やテキストサンプル、デジタルブック閲覧、講座ラインナップの説明、受講相談(Zoom/電話)などを受けられます。
さらに、講座のスケジュールや視聴期限、各種割引や合格特典の案内もあって、実際に講座を選ぶ判断材料が揃ってます。
Q. フォーサイトってどうなの?
A. 公表している合格率について、令和5年度あたりで 27.70% や 26.4% という数字が出ているという情報があります。
フォーサイトの教材は「見やすさ」「整理された構成」「スマホ対応」などが高く評価されています。
まとめ
私なりの「各種教材を選ぶポイント」をまとめてみました。
・まずは気軽に試して比べてみることが大事。最初から完璧を求めなくてもOK。
・私のやり方は「独学でスタート → 続けられなかったら通信講座へ切り替え」。これくらい柔軟な方が気楽。
・YouTubeもいい味方。「図解でわかる 社労士講座」や「社労士24」など、スキマ時間の確認用にぴったり。
・通信講座を考えるなら、講義のわかりやすさや質問できる体制、そして自分に合ったペースで続けられるかをチェック。
・教材を選ぶときは「価格」「わかりやすさ」「生活スタイルに合うか」の3つを意識すると失敗しにくい。
・高額な講座にいきなり飛びつかなくても大丈夫。まずは低コストで試して、「これなら続けられそう!」と思えたら次のステップへ。
・本屋でテキストを手に取ったり、サンプル動画や資料請求で雰囲気を確かめるのもおすすめ。
・勉強は教材だけじゃなくて工夫次第。私も「時間配分」「隙間時間の活用」「眠気対策」など、自分なりに実験中。
・結局大事なのは、「続けられるかどうか」。一度決めても、合わなければ切り替えてOK。
資格勉強のスタートは教材選びから。
焦らず、試しながら、自分に合う方法を見つけましょう^^
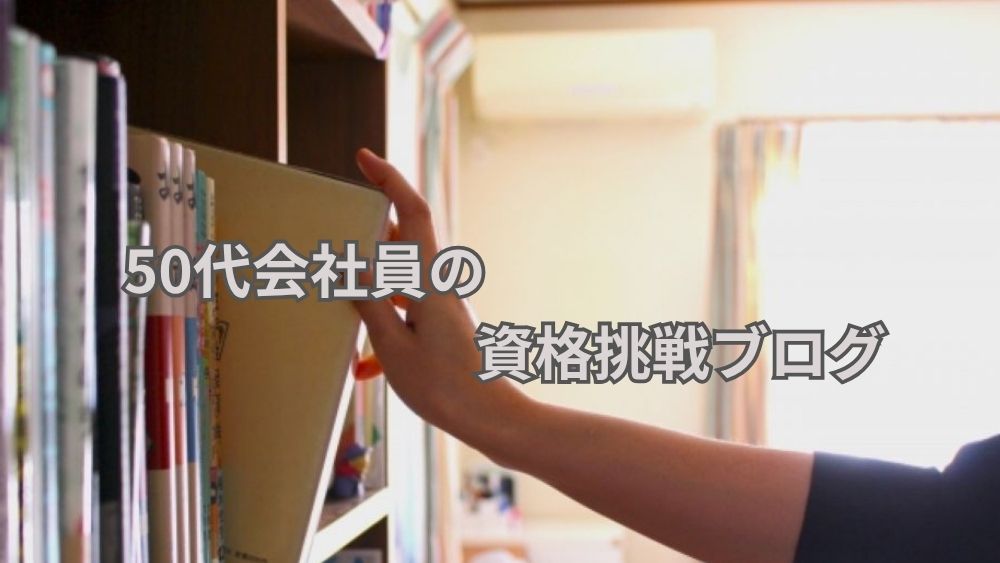


コメント